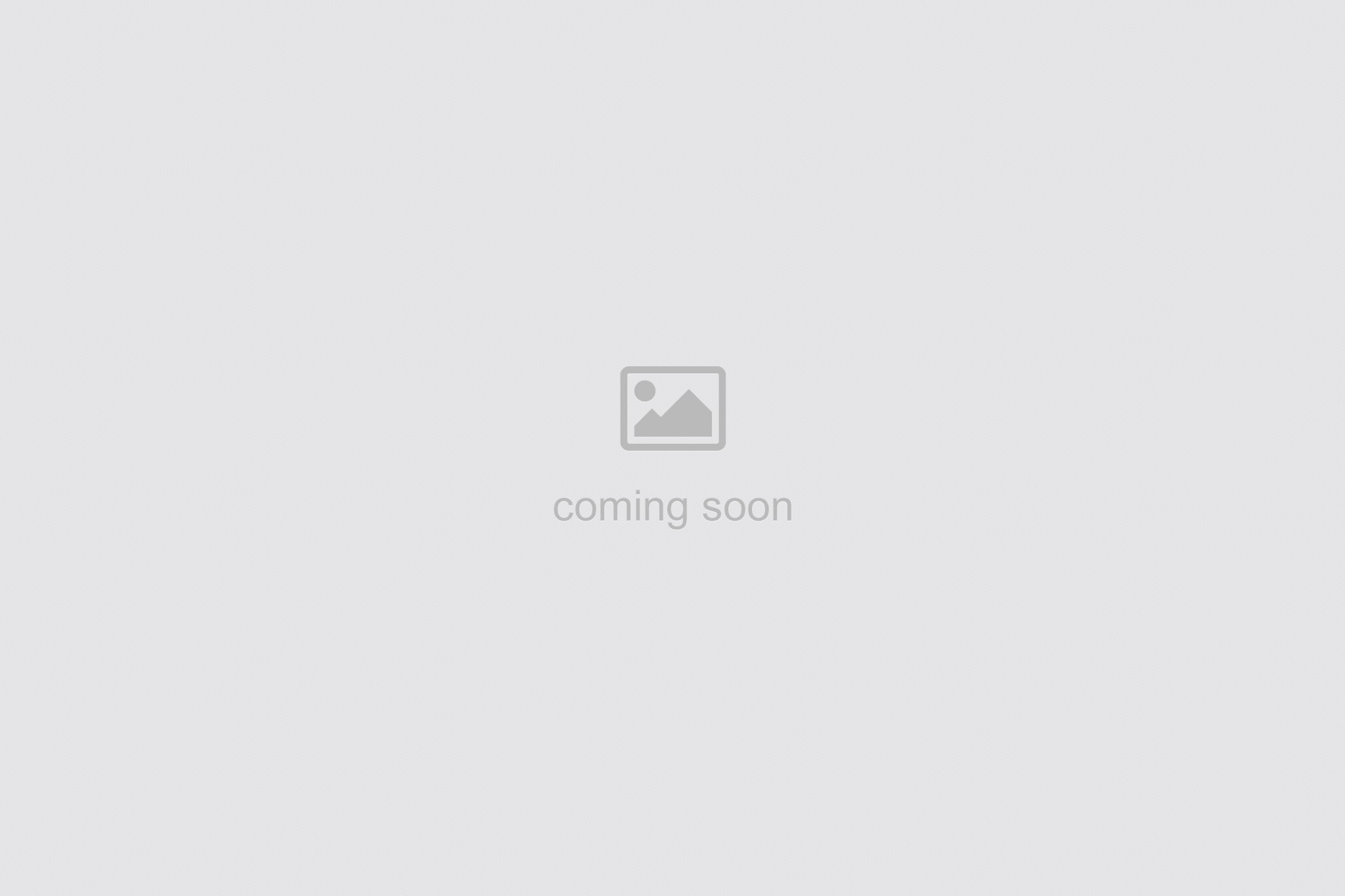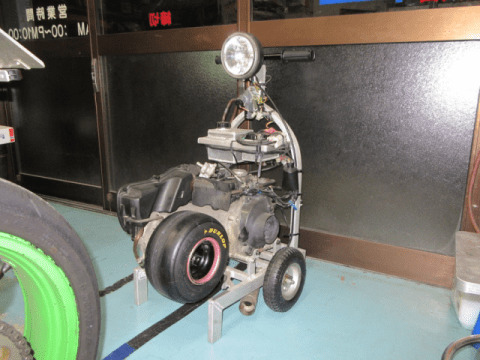カスタマイズについて
カスタマイズ事例
カスタマイズ テスト報告
パドックⅢ カスタマイズ計画 ブログ
ワイヤーハーネスKIT製作Ⅱ・Z1-R
2024-07-22
NEW
先日、Z1-Rで初製作して紹介(製作自体は冬場)した「ワイヤーハーネスKIT」でしたが、実は以前に構想だけはしていたことがありました。やはり同じZ系の「ヒューズ」が1個(メインヒューズ)しかない車両で、「多系統ヒューズ式」に作り替えることが出来ないか?と考えたからです。その車両は、当店で一貫してカスタマイズを施している「17インチZ1-R」でした。
この車両は以前に紹介したように、電装系が「18インチカスタムZ1」からの移植ですので、メインハーネスなどの基本となるパーツが「Z1仕様」となります。とはいえ純正部品ではなく、「PMC製」の復刻品に換装していました。強化タイプ(配線容量UP)になっているものの回路はZ1純正を踏襲しているので、メインヒューズだけのハーネスKITです。
その後、充電系を´11ZX10R流用にしたり、メーター/灯火類を次々とカスタマイズを施しましたので、トラブル対処を想定すると、大きな懸念を感じていました。そこで「多系統ヒューズ式」にいくらかでも簡単に出来ないか考えてみたのでした。
「多系統ヒューズ式」の回路を想定して仮構築してみると、メインヒューズだけの回路とでは根本的なところに違いがあり、元のハーネスを「加工」したり「割り込みハーネス」を追加するような手法では、ほぼ不可能と言えることが判りました。あとは1から作るか、そういったものが販売されるのを待つか?なのですが、後者ではひとつ問題がありました。この車両では、フレームレイアウトの違いやフレームマウントのカウリング仕様にした影響で、メインハーネスと電装品の配置が合わない部分が多く、かなり無理・無駄(余計な延長処理など)の大きいハーネスの取り廻しになってしまっています。他社から製作された製品では、この問題は解消されないのは当然なので、いつか作る機会(トラブル対処)があれば挑むことにして様子を見ることにしていました。
そうした間での、この度の「ワイヤーハーネスKIT初製作」でした。いろいろな仕様違いはあるものの「基本的な考え方」はこちらのZ1-Rでも変わらないので、今度は自信を持ってお勧めしたところ、続いて製作することになりました。製作したワイヤーハーネスKITの基本的な特徴は、前作とほぼ同様になっていますが、2点の異なる仕様を設けました。
まずは、大元の電源回路に「メインリレー」(パーキング回路には不介入)を装備させました。これは、メインスイッチON回路の「電圧降下抑止」と「接点の保護」のためです。※メインスイッチ内接点には、リレーを作動させるための小さい電流しか流れなくなります。
もう一つは、「パーキング回路」です。こちらのZ1-R(Z1電装)では、元々「P=パーキング」は、日本でも一般的な「テールランプ点灯」でしたので、そのまま踏襲しました。この回路には純正のダイオードKIT(カプラー接続)は使わず、市販の大容量ダイオードを回路内に組み込みました。
※前作で「メインリレー回路」を設けなかったのは、オーナーさんが元々遠方の方で転勤も考えられる仕事(現在の勤務地は近隣)に就かれているため、当店以外でも電装系整備をしやすいように出来るだけシンプルな回路を目指したからです。
※もう少し複雑な回路になるものの、´90年代のキャブレター車までならば「ワイヤーハーネス製作」は可能そうです。興味のある方はご相談ください。(一部の入手困難なカプラーの場合は、元のハーネスから切除して再利用することも考えらますが)
ワイヤーハーネスKIT製作・Z1-R
2024-07-06
足周り換装を終えて、ひと段落したと思っていた「Z1-R」でしたが、その後オーナーさんから新たなご相談を受けていました。最大の不満であった車体・ハンドリングの問題が解決されたことで、もう一つの不安も解消してしまいたいと相談に来られました。
それは、この車両を手に入れられた時から不安を感じられていた、「電装系」に関してのご相談でした。
手に入れた直後から、点火系にはASウオタニ製SPⅡフルパワーKIT(デジタル制御フルトランジスター点火方式)を、充電系にはMFバッテリーとPMC製ICレギュレーター(MFバッテリー対応)に換装して、信頼性と基本性能を上げるようにされていたそうです。
加えてハンドルスイッチは、右側はスロットルKITに合わせてOWタイプに、左側は復刻品の新品に交換されたのですが、そこで問題として残ったのが、メインハーネスをはじめとした「配線類」だったようです。
この車両に装着されていたのは、純正のメインハーネスそのままではなく、「3系統ヒューズ(通常の自動車業界では見かけない物)式」になっていたそうですが、後から手を加えている(Z1-Rは本来メインヒューズのみ)のは明らかで、どの系統か不明な上きちんと機能しているかも心配な状態だったようです。しっかりした新品に換えたいと思い、出来れば「多系統ヒューズ式ハーネス」が良いと製品を探してみたものの、Z1-R用はなかなか見つからず、なかば諦めていたそうです。
それでも世代(Z系として)の近い「Z1000MK-Ⅱ」用の製品がみつかっていたようで、これが何とかならないかとのご相談にみえられたのでした。目を付けられていたのはPAMSさん(Z系カスタムショップ&オリジナルパーツメーカー)の製品(多系統ヒューズ式)でした。
これまで、電装系の組み合わせのために配線を加工したり、部分的なサブハーネスを製作することは多々経験してきたので、物によっては流用加工が可能かもしれないと、ひとまずトライしてみることになりました。
取り寄せたPAMS製ハーネスKITの回路を調べてみると、メインリレー回路追加・多系統ヒューズ・オートライト回路(北米仕様?MK-Ⅱの常時点灯式ヘッドライト対応)となっていて、かなり「凝った回路」になっていました。特に、カワサキ純正ジャンクションボックス(ヒューズボックス&サーキットリレー内蔵)に加工を施された回路が複雑で、メインスイッチをはじめとしたZ1-Rとの違いも多く、これをさらに流用加工するのは、かなり困難で断念せざるをえませんでした。
結果、当店では初の「メインハーネス製作」を手掛けることになりました。
製作にあたり狙いは、あくまでも「多系統ヒューズ式」を主題として、後々のトラブル発生時に故障診断や修理・修復をしやすいことを考慮した回路・配線構成にすることとしました。そのため、多系統ヒューズの他には、特別な回路は極力加えないことにしました。
実際の製作においては、出来れば純正配線の色分け(メーカー毎に各系統に使用する配線色は決まりが有ります)を再現したいところですが、現在当店で入手可能なのは約20色(一般的な回路に多く使われる配線の容量AV0.75)程度しかなく、また、さらに大容量のAV1.25/AV2.0では数色しかないため、ある程度置き換えて使わなければなりませんでした。
途中、いくつかの繋ぎ直しをしながらも完成に漕ぎ着けました。
※製作したハーネスKIT(スイッチ類の部品側の配線加工を含みます)の特徴は以下のようになります。
1:メインヒューズ(メインスイッチまでの常時電源)+サブヒューズ(パーキング系と追加電装品のための常時電源取出し用)
2:4系統ヒューズボックス(ホンダ純正品流用)画像④
イグニッション(点火)系/ヘッドライト系/ストップランプ系/その他の一般電源系
※スターター系(セルモーター回路)は、点火系と分離して「一般電源系」に入れています。
3:電装の中でも重要な「点火系」と「充電系」のハーネス(配線の束)は、メインハーネスと分離させて、電源線など必要最小限の配線のみメインハーネス内に収めています。
4:電流の大きさに合わせた配線容量(上述のAV0.75~2.0)の選択
※ヘッドライトHi/Loの回路など、純正色(赤/黒・赤/黄)を踏襲しつつAV1.25にしたくても配線が無い場合には、AV0.75配線を2本束にして製作しています。(アース用黒/黄線は合流しつつ計3本)
5:唯一特別に、メインスイッチ回路に「直結防止(抑止)回路」を設定しました。
6:リヤ周り(テールランプ・リヤウィンカーなど)のように、同じ本数で配線が長くなる場合、メインハーネスは短目でカプラーに収めて、「延長サブハーネス」をカプラー接続するようにしています。※これも診断・修復をしやすくするためです。
きちんとした純正ハーネスとスイッチ類ではなかったため、最後まで確定出来ずにいた「P=パーキング」回路でしたが、最終的に「ハザード対応」だということに行き着きました。そのため、最後に独立した「ハザード回路(画像⑦)」を製作して組み込んでいます。ハンドルスイッチ内にはハザード用スイッチは無いので、別にスイッチ単体をハンドルパイプに設置しています。
※この回路では、通常のメインスイッチ「ON=走行中」でもハザードは動作出来ますし、「P」位置でも、ハザードスイッチを入れれば動作させることも可能です。
※画像では、左右ハンドルスイッチ接続用カプラーが全て「クリア色」になっていますが、より接続間違いのないように、一つ(6極)を後ほど入手出来た「黒カプラー」に組替えました。
※以前、製作した「メーターパネル」ですが、アルミ製なため日光が反射してまぶしいということで、カーボン調ラッピングを施すことになりました。選んだのはラッピングフィルムより強固な「3M製ダイノックシート」です。画像⑧
続・実験キックペダル・SR
2024-06-15
前作に引き続き、さらに「短いキックペダル」を作って実験してみました。
前作では有効半径165mm(WM製に比べてマイナス15mm)だったところを、さらに15mm短くして有効半径150mmに設定して製作しました。長さの他は1作目と基本的に同様の仕様としています。はたしてどんな結果となるのか?
結論として、とても使えたものではないことがはっきりしました。
短くした効果は、ピストンの位置出しの段階で変化が感じ取れました。デコンプ(エキゾーストバルブを開く)しつつ空廻しをして適した所で止まるようにしているのですが、クランクシャフトの周りが良すぎて通り過ぎてしまう勢いでした。
この勢いに期待も膨らみましたが、何度か回し直して適したスタート位置を出して踏み込もうとすると、踏み始めが重すぎて、とても勢いを出すどころではありませんでした。そこで本来ならば、あまり適さない位置(かなり通り過ぎた=ペダルは低い位置)までずらしてみると、踏み込めるようにはなりましたが、それではエンジンは始動することは出来ませんでした。短すぎることは分かったものの、踏める限界点を探る意味でも、しつこく(20回以上)チャレンジし続けましたが、結局はエンジンを始動出来ないまま諦めることになりました。
かなり疲れたこともありますが、もう少しで掛かりそうとなったところで、キックペダルが後ろ向きに回ってしまったのでした。ここで強度の問題が出たのでした。
すぐに取外して確認すると、ストッパー部はえぐれたように変形(画像②)していることと、軸受け部が一方向に伸びて開いて(画像③)いました。キックバーの根元にも少し曲がりが見られました。
アルミ材では強度的に難しいとは考えてはいたものの、かなり厳しい結果となりましたが、アーム長さに関してはおおよその結論は得られました。一作目の有効半径165mm付近が、現状(現在のエンジン仕様と自信の体格・体重・脚力の組み合わせ)では適正値だと確認出来ました。
強度不足に関してはかなり厳しそうですが、それでもいくらかの対策を考えられそうなので、もう少しアルミ材(7N01)を主体として試作してみようと思います。
※純正キックペダルの長さ(有効半径185mm)は、ある程度体重の軽い方や脚力の弱い方でも踏み込めるように配慮した設計になっていると思います。さほど小柄ではなく慣れた方ならば、ノーマルエンジンのSRでは蹴り応えをあまり感じられないくらいではないでしょうか。
※キック中に何度か「ケッチン=キックペダルの跳ね返り」を受けましたが、軽量・ショートタイプにした効果の副産物として、衝撃が軽くなっていることを発見しました。股関節にまだ痛みを感じる身としては、非常に助かりました。
実験キックペダル・SR
2024-06-01
急遽、思いついた発想を実証してみたくなり、SRの「キックペダル」を製作してみました。
昨年の事故以来、負傷した右脚の影響で当店のSRはエンジンを掛けられず(ノーマルエンジン車は2月頃にはなんとか掛けられました)にいました。その後リハビリの甲斐もあって、かなり回復してきたので、5月に入って間もなくの頃、いよいよエンジン始動にチャレンジしてみることにしました。※エンジン始動さえ出来れば、乗ることは大丈夫そうなので。
発想の発端は、この時です。
約10か月ぶり(しかも横倒しになってエンジンが止まったままの状態)のエンジン始動ということも大きい原因であるものの、なかなかエンジンは掛かりませんでした。諦めようかとも思いましたが、20回程度キックを試みて何とかエンジンを始動することが出来ました。
キックをしている間に感じたのが、エンジンを回す「勢いが足りていない」ということでした。SRのキック始動の要領は、よく動画などにも揚げられてていますが、ようは体重を掛けながら一気に踏み込んでクランクシャフトを勢い良く回す(速い回転速度)ことです。
右脚・股関節は痛みを感じることもなく、踏ん張るような脚力は戻ってきているものの、瞬発力はまだまだ足らないようでした。そこで考えたのが、この脚でも勢いを増して回転速度を上げる方法です。
それが、「キックペダルの短縮化」でした。
キックペダルの踏み込みは、その基部のキックシャフトを回して(その後ギヤを介して増速してクランクシャフトを回す)いるので、キックペダルのアーム長(有効半径)が短くなれば、アーム先端の「踏み込み速度が同じ」であれば、シャフトの回転速度(角速度)は「速くなる」ことになります。※その分、踏み込む力を大きくする必要があります。
その発想を実際に試してみたいと思い、短いキックペダル(アーム部のみ=ボス部は純正)を製作することにしました。
以前から、軽量化のために軽合金製ペダルにしたいと思っていましたので、まずは、アルミ7N01材(溶接に適したアルミ合金の中では強度は最高クラス)で製作してみました。※アルミ製ペダルは、どこのメーカーも製作していないことから、かなり強度に無理があると思われます。あくまで実験ですので、どこに問題があるか洗い出し、対策法があるかを考えるのも目的です。
これまで使っていたWM社ペダル(有効半径=180mm/純正=185mm)に対して、有効半径を15mm短い165mmに設定して製作しました。固定式ステップバーを避けるオフセット量も、当店のSRに合わせて小さくしています。軸受部付近の形状はWM製とは変えて、溶接強度を上げるための工夫を施しました。※この部分の溶接は当然のことながら、中心までの全溶接です。さらに溶接ビードの盛りを多目にしています。
軸受部35mm径・アーム部20mm径・バー部15mm径の丸棒としてストッパー部8mm厚板材の4個の部材を溶接して組み立てています。※ペダルラバーのストッパー部はボルト固定
製作してすぐにエンジンに仮組みして、しなりなどのチェックをしましたが、結構しっかりとした感触でした。
本組みし直して、いよいよエンジン始動を試してみると、少し重くは感じるものの、苦にはならない程度で踏み込みが出来ました。そしてクランクシャフトの回転は確かにいくらか勢いが増していました。1回目のキックでは始動には至りませんでしたが、空回りの様子が変わったのが確認出来ました。
そして、2回目のキックであっさりと掛かりました。その時は、キック始めのピストン位置が最適位置ではなく若干過ぎたところ(ペダル高さでは低目から始まる)踏み始めていて、ここからでは掛からないかと思ったものの、思ったより勢い良くクランクシャフトが周り始動出来たようです。※ちょうど、これまでのベストな位置から踏み始めた際の回り方と同じような回り方です。
短くした成果(強度や耐久性は別として)を確認して、気を良くしました。
本来ならば、このまま使い続けて強度に関する結果を確かめるところですが、それよりも、アームの長さの最適値の方が気になり、さらに短い物を作って検証することにしました。そちらは後日報告します。
※SRは、キック始めの位置出しの際に、カムスプロケットに取付けられたインジケータを見て位置合わせをしますが、ある程度の範囲があり毎回最適なところに合わせるのは、結構むずかしいことです。
足周り換装(フロント編)・Z1-R
2024-05-22
Z1-R足周り換装は、リヤに続いて「フロント周り」です。
主要構成部品は、オーリンズ製正立43mmフロントフォーク(XJR1200用)・ウィリー製Z1用ステムセット(35/38mm可変オフセット式)・ゲイルスピード製TYPE-Nアルミ鍛造ホイール(3.00-18/タイヤ:Q5A110/80ZR18)・APロッキード製対向2ピストン鋳造キャリパーとなります。
フロント周りの主軸(構成上の)となるのは、「オーリンズ製フロントフォーク」です。オーリンズ社としては、Z1など(ステアリングステムセットの換装が必要な車種)には設定が無く、「XJR1200用」の800mmバージョンを各々のショップで流用していました。またたく間に人気が上がり、オーリンズ正立フォークのための「Z1用ステムセット」は、カスタムパーツメーカー各社から販売されるようになりました。
その中で選んだのが「ウィリー社製」でした。決め手となったのは、「可変オフセット式」でした。当時から17インチホイールへの再変更を想定していたわけではなかったものの、進化した「18インチラジアルタイヤ」の特性が分からない状態でしたので、セッティングの幅(選択肢)を広げるために、こちらをお勧めしました。※もちろん「ウィリー」さんの製品のクオリティの高さは一級品です。
実際にZ1(18インチ仕様)に装着すると、オフセット38mmで良好なバランスでした。※その後に「Z1-R」では17インチラジアルタイヤに合わせてキャスターを立たせたので、オフセット35mmに入れ替えてディメンションを整えることが出来ました。
そこで今回の「Z1-R」では、38mmに設定し直して装着します。装着に当たって「ステムベアリング」には、良好な動きをもたらす「テーパーローラーベアリング」を使用したいところですので、作業前にあらかじめPMCさんのサイトで確認したものの、Z1-R用の製品が見つかりませんでした。Z1系との違いが判らないままでしたが、とりあえずZ1用を用意して作業にかかり、現物を確認することにしました。
ステムシャフト径はZ1と同径でしたが、アッパー側のアウターレース径(フレーム側)に違いがありました。あらためてベアリングメーカーのラインナップを調べてみましたが、既成サイズとしては存在していないようでした。
幸いにして、この車両には元々テーパーローラーベアリングに交換されていて、アッパーベアリングはかなりコンディションは良かったので再使用させていただくことにしました。※重力や減速時の軸方向の荷重はほとんどロアベアリングが受け持つため、アッパー側はいくらかの軸と直交方向に働く力を受けるだけなので、比較的に傷みにくくなります。
ステム(アンダーブラケット)がフレームに取付可能になれば、トップブリッジ・フロントフォーク・ホイール(アクスル径はZ1共通)は合わせて取付可能になります。あとは、この車両にすでに装着されていた「1:APロッキード製キャリパー」・「2:純正カウリング/メーターなどの周辺機器」・「3:純正フロントフェンダー」の取付への対応になります。
1:APロッキード製キャリパー(CP2696/3696)は一般的なキャリパーと違い、キャリパーブラケット(またはフロントフォーク)への結合部が貫通孔になっています。この方式ではキャリパーの内側に位置するブラケットに対してボルトで締付けをすることになります。純正フォークに比べてスパン(左右フォークの間隔)の広がっている「オーリンズ正立フォーク」で対応させるとなると、とても分厚い形状のブラケット(汎用性を高めるためにキャリパー取付部別体式)になってしまいます。
そのため、重量面・製作コストを考えて、キャリパーの貫通孔にネジ山(ヘリサート加工・画像③)を作り外側にブラケットを位置させる方式(フォーク・キャリパー共に外側を繋ぐことになり、比較的に薄い形状)に変えて、キャリパーブラケット(画像④⑤)を製作しました。
2:Z1-Rのカウリング・メーター・ヘッドライトなどは、左右フォークにかぶせられたブラケットが主体となってはいますが、各々でも支え合う構成になっています。
そこでブラケット製作にあたり、始めにメーターブラケット一式をトップブリッジに取付けるステーを製作して位置決めの基準とします。
フロントフォークを基点にするブラケットの取付方法をどのようするか?が難題でしたが、考え付いたのが、ステアリングダンパー用フォーククランプを流用する方式です。ダンパーロッド組付け用のネジ山を削り落とし、貫通孔に加工した上で、「上下2個のクランプ」で、丸棒(両端にM8-P1.25ネジ穴)をベースにしたブラケットを支えるようにしました。メーターブラケットの基準点から各部(ヘッドライト・カウリングアッパーマウント・ウィンカー)寸法を割り出して、板材(アルミ7N01材)を溶接組立で製作(画像⑤⑥⑦)しました。※ヘッドライト光軸調整のための円弧状穴も設置しています。
3:フロントフェンダーに関しては、純正が取付不可能ならば他の物でも良いとは言われていましたが、プレートとカラーを介して純正フェンダーを取付けることが出来ました。
足周り換装が完了したのち暖かくなってから、実走してセッティング変更(一般走行向け)を施し煮詰めていきましたが、あらためて「18インチラジアルタイヤ仕様」の特性の長所を再認識しました。しっかりしたグリップ感とスムーズに旋回を始めるハンドリングになっているものの、けっして鋭すぎないおおらかさを併せ持ち、安定感も高く気持ちよく走ることが出来ます。オーナーさんも、この乗り味の変化に驚くと同時に、たいへん喜んでいただけました。
※フレームには特別に補強は入っていないものの、Z1に比べて元(メーカー)から剛性が高められているため、一般走行レベルであれば、剛性不足から起こる不安定な挙動は感じませんでした。
※サスペンションセッティングの際にフロントフォークの突き出し量の変更もしましたが、この度製作したカウリングブラケットではフォーククランプを後側から緩めるだけで作業可能になっていて、あまり手間が掛からずにすみました。